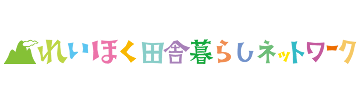アメリカで教育を学び、日本では実際の教育現場に立った鈴木さん。
二つの国で教育に関わるなか、その違いや課題を、実感として受け止めてきたと言います。
「教育で町をおこす」──そんな挑戦を掲げた町に惹かれ、2016年、土佐町へ移住。
豊かな自然、支え合って生きる人々のあたたかさ…“お金では買えない価値”にあふれる土佐町で、社会における教育のあり方を見つめ直す日々が続いています。

鈴木 大裕(すずき だいゆう)さん / 2016年10月 土佐町移住
「教育で町をおこす」という旗に惹かれて
―――土佐町に移住しようと思ったきっかけを教えてください。
友だちが先に土佐町に移住していたんです。ちょうど町長が変わったタイミングに土佐町が「教育で町おこしをする」という旗を掲げたことが始まりでした。
当時、僕はアメリカの大学院で研究をしていましたが、世の中全体が新自由主義的な発想になり、教育にはお金をかけず、各家庭の自己責任に委ねられる流れが強くなっていました。
そんな時代に自治体が “町の存続を次世代の教育に賭ける” と宣言した訳で。これはロマンがあるな、と、2016年に土佐町へ移住しました。
移住当初は地域おこし協力隊として、行政と学校をつなぐ「学校行政コーディネーター」に従事。英検指導で学校にも入りましたね。その後、教育系NPOへ活動の場を移し、2019年には町議会議員選挙に出馬。現在は教育研究者としての執筆や講演と、土佐町議会議員としての活動をしています。 また、毎週水曜日には朝7〜8時、夕方4〜5時、5〜6時の3クラスで、中学生向けの英検教室も開いています。町の子どもたちと触れ合えるのは、自分にとってもすごく大切な時間です。
16歳で単身アメリカへ──「生きてる実感」を初めて得た高校時代
―――高校時代にアメリカへ留学されたと伺いました。どんな思いで海外に渡ったのでしょうか?
はい、16歳で単身アメリカに渡りました。
中学は殺伐としていてつまらないと感じていて、高校受験を頑張って自分の行きたい高校に入ったんです。何か見える景色が変わるかなと願って。ですが、環境は変わっても、見える景色は変わらなかった。「このままサラリーマンになる未来」が高1の冬に見えてしまって、それが嫌で親に相談し、その半年後にはアメリカ行っていました。
英語も特別できたわけではなく、初めての単身アメリカ生活は本当にサバイバル。ですが、それがむしろ嬉しかったんですよね。誰かに生かされているんじゃなくて、じぶんで“生きている”気がして。
良い先生との出会いもあり、人生で初めて“学んでいる”と感じました。それまでの日本の教育ってなんだったんだろうーーーーって思うほどに。その経験から、教育学を学ぶためにそのままアメリカで大学、大学院へ進学しました。
卒業後は、日本の教育システムに疑問があったので、自分の経験を還元したいと帰国。通信教育で2年半かけて教員免許を取得した後、千葉県の公立中学校で6年間英語教諭として教壇に立ちました。予想以上にハマって、仕事にやりがいも持っていましたが、「なんで教員になったの?」と、誰に会ってもそう聞かれることには衝撃を受けました。
そこには“もっと他にいい仕事あったのに”という空気がある。教員が尊敬されない社会、という現実に直面したんです。教員の社会的地位の向上なしに教育改革は進まないと感じ、自分の発言力をつけるため再びアメリカの大学院へ戻りました。
アメリカの教育改革の“光と影”
―――アメリカの教育現場に身を置く中で、公教育についてどんな違和感や問いを抱くようになりましたか?
当時アメリカでは、大胆な教育改革が進んでいました。
能力のある先生の年俸制度や、やる気のある先生が自分たちで学校を作るチャータースクール制度など、魅力的に見える部分が多い一方で、研究を進めるほど、公教育の市場化が家庭間・地域間格差を生んでいく現実も見えてきました。
私が子育てをしていたニューヨークでも、「市場型」学校選択制を徹底していました。たくさんの学校説明会に行く時間のゆとりや、高い情報処理能力をもつ家庭は良い学校を選び、それがない家庭の子どもは“誰からも選ばれなかった学校”に行くしかない。義務教育なのに当たり外れが生まれてしまうんです。そして、学校が学力標準テストの点数で評価されるものだから、いわゆる「底辺校」は朝から晩までテスト対策に終始する。そして皮肉なことに、裕福な地域の学校ではテスト対策とは無縁の全人教育をするんですね。テスト対策しなくても点数を取れるような、社会的資源が裕福な家庭の子達が集まってくるわけですから。
「なにをもって“公”、なにをもって“教育”と呼ぶのか?」という本質的な疑問を突きつけられました。
選べる人間が選び続けていたら、公教育なんて良くなるはずがないからと、妻に相談し、我が家は“選ばない”という選択をしました。そしたら案の定、娘たちが通うことになったのは、まさに“誰からも選ばれなかった学校”。周囲はほぼ生活保護を受けている黒人の子どもたちで、生徒の5人に1人がホームレスという過酷な状況でした。経済格差が肌の色となって表れていました。当時大阪を中心に日本に広がりつつあった市場原理に委ねた教育改革は、日本にそのまま持ち込むべきではない──そう強く感じた出来事です。 2016年、著書の出版と同時に日本へ帰国。市場原理的な教育改革に抗うなら、舞台は都市ではなく地方だと確信し、土佐町へ向かいました。
“お金で買えない価値”があふれる町で
―――土佐町に来て、ご自身の考え方や価値観に変化はありましたか。
逆説的に聞こえるかもしれませんが、土佐町の魅力は町に学校が“一つしかない”ことだと思っています。選べないからこそ、「この学校をどう良くするか」というパブリックな意識が生まれる。都市部のように「合わなければ隣の学校へ」という発想にはならないんです。
だからこそ、本気を出せば唯一の町立学校を私立顔負けのユニークな学校にできる。嶺北の大自然の中で真の「生きる力」を磨き、少人数学級だからこそ、多様な生徒一人ひとりの自己実現を支援できる。都会でそれをやれば、単に富裕層の受け皿にしかなりませんが、過疎地でやれば移住促進にもつながっていく。
僕の子どもたちは、小3と小1の頃にニューヨークから土佐町に来ましたが、彼女たちが一番驚いていたのは「自分たちだけで歩いて学校に行けること」ことでした。ニューヨークでは、治安の問題上、5年生までは一人で留守番すらできず、通学も公園も常に保護者同伴。それが当たり前だったんです。
ここでは「行ってらっしゃい」で自分たちだけで歩いて学校に行き、帰ってきたらランドセルを置いて遊びに行ける。その自由が、彼女たちにとって最大の驚きだったのです。 どちらの暮らしも両極端で、それを経験できたのはすごく大きかったです。教育で思うことはあるものの、ニューヨークでの暮らしもすごく楽しかった。ただ、ひとつどうしても嫌だったのが、子どもたちを守るために“人を疑うこと”を教えなければならなかったこと。何かもらっても食べちゃダメ、誰かに声かけられてもついてっちゃダメ。
でも土佐町に来たら、逆に「人っていいものだよ」って、教えながら子育てができた。これはかけがえのないことです。
―――土佐町の人たちとの関わりの中で、印象に残っていることはありますか。
土佐町に来て僕自身も驚くことがたくさんありましたね。単身赴任で来た当初、風で倒れた物干し竿をそのままにして出勤したら、帰宅時にお隣さんが立て直してくれていたんです。「倒れちょったき、直しちょったよ」と。
人の家の庭に入って、何気なくそれをやってくれる。その感覚が、本当に信じられないほど温かかった。そんな、家族ではない他者との優しい気遣い、関わりがここでは日常的で、当たり前なんです。
この土佐町は、「お金では買えない価値」にあふれている。
こういう価値観って、もっと広めていかないといけないと思っています。“人間っていいもんだな”、“自然とともに生きるって豊かだな”って思えるような価値観が広がれば、きっと田舎に行こう、土佐町で暮らしてみたいって思う人も増えるはずです。
ここで過ごしてもうすぐ10年になりますが、この町でなら教育も子育ても、人とのつながりも、ちゃんと未来につなげていけると感じています。